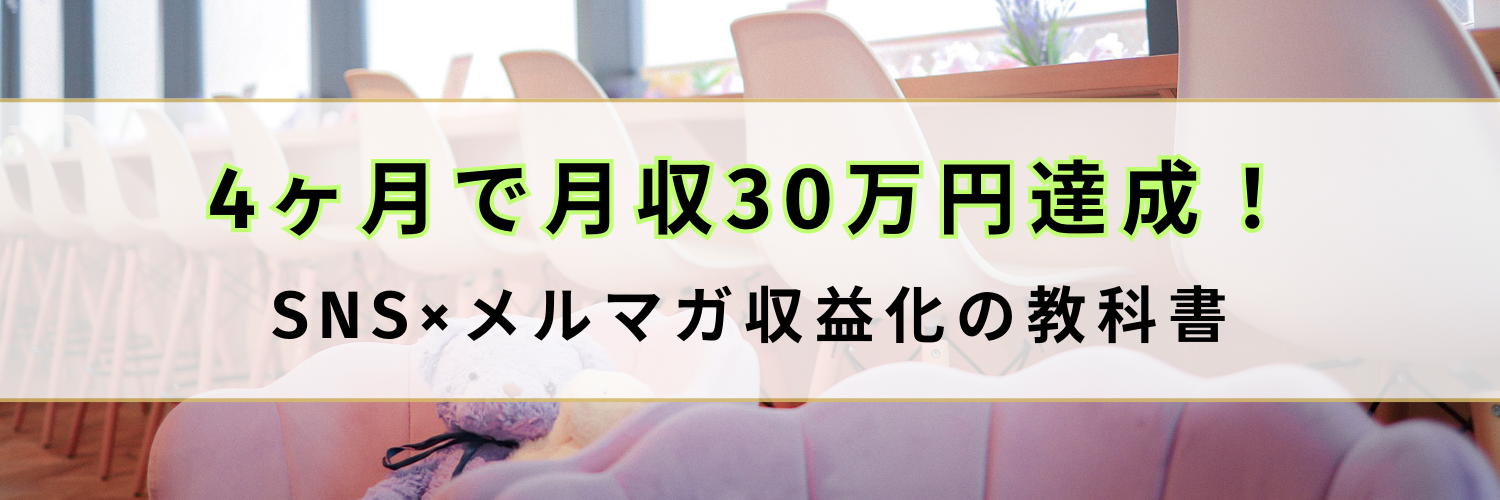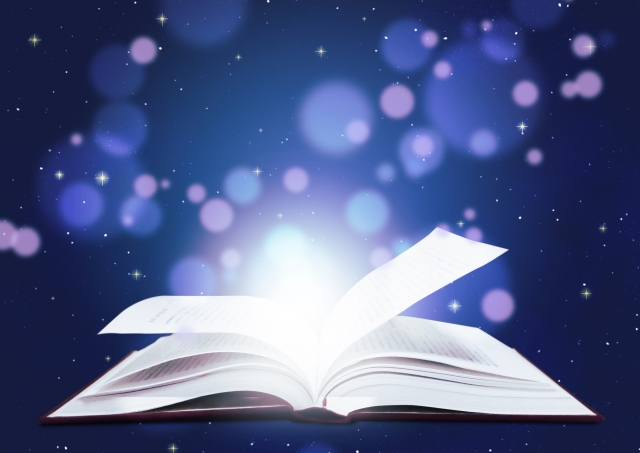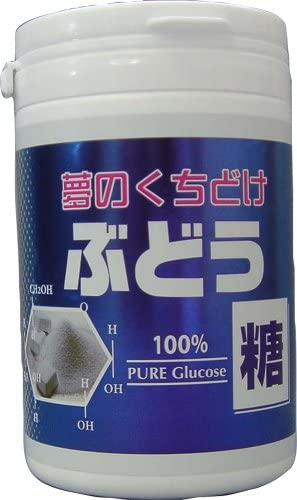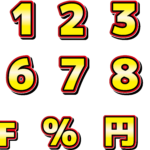Harvest、値上げ後も次々とご購入いただいています。
本当にありがたいです。
これからも内容をアップデートし、
サポートもご提供していきます。
同時にコンテンツ実践時に大切なのが、
正しいノウハウを、
正しく実践し、
結果が出るまで継続
をすることです。
当たり前の成功法則ですが、ここで
つまづいてしまう方が多いのも事実。
そこで今日は1つ、行動・継続・習慣化の
コツをお話します。
以前、Xでこんなポストをしました。
「ネットビジネスで挫折しやすいのは
ネガティブな人ではなく、
ポジティブなフリをする人です」
よく自己啓発や成功法則の世界では、
ネガティブ思考よりもポジティブ思考が重要
と言われます。
が、私が見てきた中だと、成功者は
「意志の強いネガティブ思考」
が多いです。
日々の考え方は後ろ向きですが、
夢や目標だけは諦めません。
どれくらいネガティブ思考かと言うと…
■次の報酬が銀行口座へ入金されるまでは使わない
「○日にお金が入るからこれ買っちゃおう」
ではなく、お金が入ってから買う。
何かのトラブルで入金されなかったり、
報酬がなくなるかも知れないため。
■セールスでは、あらゆる失敗の可能性を考えて備える
「ここで購買意欲が下がらないか」
「ここでガッカリされないか」
「この言い方は誤解を生まないか」
など、失敗するケースを徹底して探る。
「失敗する選択肢をすべて消せば、
結果的に成功する」というニュアンス。
■セールスレターを書いたら何回も読み直す
自分で3回、5回、10回と読み直す。
誤字脱字1つもないよう、
周りの方々にチェックのお手伝いを
依頼することもある。
このように、あらゆるネガティブな可能性を考えます。
ものすごく慎重であり、完璧主義。
逆に「これでもう行けるっしょ!」と
ポジティブに考えすぎる人は、悪く言うと
ギャンブラー思考とも言えます
なので実践が「これくらいでOKでしょ」と
粗削りになってしまい、結果が
出なくなりがちです。
そのためポジティブ思考って必ずしも、
メリットばかりではありません。
しかも人間の脳って元々、
ポジティブとネガティブ
を両方感じるものです。
ネガティブになり過ぎるのはよくないですが、
ポジティブ思考だけなのも不自然なんですよね。
生きていたら必ずネガティブな考えが浮かびます。
そこを無理に抑えつけても、
「ネガティブを見て見ぬフリをしている」
「言葉だけ強がってポジティブ」
と、隠しているだけになりがちです。
そうすると、溜まりに溜まったストレスが
いつか爆発し、ポキッと心が折れてしまいます。
ポジティブでエネルギッシュだった人が、
急に失踪するのは、無理して耐えていた
ことが原因だったりします。
私自身も、そうして明るく振る舞っていた結果、
急に燃え尽きてしまった経験が何度かあるんです。
なのでネガティブ思考もときには必要です。
だからと言って、あまりに悪い方向にばかり
すべてを考えてしまうと継続ができません。
(とは言え、そこまでネガティブな人は
ネットビジネスに挑戦しないと思います)
だから私がオススメしているのは、
両方をバランスよく使い分けること。
まずはネガティブ思考を有効活用して、
「いかに失敗しないか」
を考え抜くんです。
Harvestも販売ページは
Ver1からVer7まで書き直しましたし、
リリース後もすでに7回近く、
更新しています。
※知らなかったんですがBrainが更新されると
購入者さんに通知されるようで…
めっちゃ通知まみれですみません(笑)
音声も
「ここからここまでのクオリティが低い」
と思ったものを6時間近く、
丸ごと録り直しもしました。
「これでもう大丈夫でしょ」という
ポジティブ思考ではなかったんです。
むしろ日々の細かい作業は、
ネガティブ思考のほうが上手くいきます。
代わりに、
「そうして努力・行動・継続したことは
必ず成果になる」
という未来に対してはポジティブなんです。
成功者はこの傾向を強く持っています。
いちばん危険なのは、この逆。
「俺はこの教材で絶対成功する!」
と目の前のことはポジティブなのに、
「どうせまたノウハウコレクターだろうな…」
と先のことはネガティブだと悪い結果を生みます。
目の前のことを慎重(ネガティブ)にやっているから、
未来は必ず明るくなる(ポジティブ)
このバランスがいちばんオススメです。
慎重にやっている分、結果が出やすくなりますし、
未来に対しては前向きなので継続できますし、
ネガティブもポジティブも両方使えます。
脳は前向きにも後ろ向きにもなるもの。
どちらか一方に偏るよりは、バランスよく
両方を使い分けていきましょう。